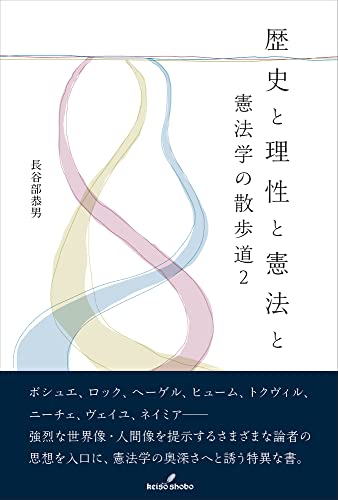夏の文楽公演は二度に分けて見物。十年前と違い、二部続けてはとても無理。腰が痛くなって見物どころではない(もっとも十年前だって楽ではなかった)。そのぶん前後の時間に多少余裕はあるのだけど、この猛烈な(災害級というんですか)×××のなか、ましてたださえ××苦しい大阪の街中を歩くのはどうにも気ぶっせいで、いつものうどん屋・割烹・鮨やもよしとする。
※目から耳から散々流し込まれて皆様閉口でしょうから、一部伏せ字と致しております。
まずは第三部の『夏祭浪花鑑』。米朝師匠が、いかにも懐かしそうな口調で「昔は浪花の俠客の芝居をようやってましたな」とおっしゃっていたのを思い出した。それくらいこの俠客なる人種というのは気疎いものなのである。義理や面子、男気を重んじるというのは観念的にはわかるが、舞台で観る立場から「いよっ、俠客かたぎっ!」とはまったくならない。なんだか無気味なものがそこにごろっと転がってる、というほうが実感に近い。
これは貶してるのではなく、むしろ今回玉男さんの遣う団七にひどく感銘を受けたことを言いたい。まず、「長町裏」で惨殺される舅義平次が悪人ではないとうことがある。義平次がしつこく述べ立てるように、このおっさん、団七のことをよう世話してるのである。無論だから義平次が善人とは到底言えなくて、あこぎでイヤな奴には違いない。で、ここが微妙なところなのですが、義平次とのやり取りから殺傷に及ぶ場面で、素直にとるかぎり、団七はけして舅のことば・振る舞いに感情的に逆ギレしてはいない。かといって俠客としての一分が立たないゆえにやむなく一線を越えたのでもない。逆鱗に触れるという古諺があるが、その本源的な意味において団七は怒っている。つまり余人には理解も予測も出来ないところにに分別も情けも喪わせる「鱗」があって、いったんその力が解き放たれたならば、暴虐はおよそ自然災害のようなもので、けちでねちこく胴欲な、とはつまるところ世間並みの「イヤな奴」に過ぎない初老の男などにはとても防ぎようもなくただただ切り刻まれ、足蹴にされる他ないのである。
「住吉鳥居前」で、団七・一寸徳兵衛が一瞬で意気投合するくだりの気味悪さもこの線に沿って見ると腑に落ちる。玉島兵太夫に恩ある身、という徳兵衛自身が説明する理由はいかにも空々しくひびく。あれは化け物同士だからこそ伝わる世界なのだ。再び言うが、世の民草はその突発的な暴力には慴伏し、ときに無残な犠牲となるばかり。だからつむじ風(むしろ妖異かまいたちとすべきか)がひとしきり荒れ狂ったあとに、それでも世界を元通りに縫い合わせようとし、またそうする他ない生が憐れなのである。
あまりに近代的に過ぎる解釈だろうか。江戸の作者がそこまで考えてはなかろう。否定はしない。しかし少なくとも団七の玉男さんと義平次の和生さんは、「今の自分たちがこの芝居をするならこう演じるしかない」と考えて遣っているのだろう、と推測する。そこに抜き差しならない「リアル」があるのだと思う。殺し終わったところで幕切れとせず、ひと呼吸あって「八丁目さして」闇へ走り込む姿がじつに生々しかった。
それに比べると、第二部『妹背山婦女庭訓』の「入鹿誅伐の段」はなんだか悪い意味で芝居じみていて、普通にはよりスケールの大きな《悪》であろう入鹿がちっともコワくない(ま、入鹿の姿勢がめりこみがちで柄が小さく見えるせいもある)。直前に見せられるお三輪の最後が可哀想で、付け足りにしか映らないのか。おなじ公卿悪でも、車引の時平は無気味だからなあ。うん、それにしても勘十郎さんのお三輪、殿中で官女にいびられながらふらふらと立ち上がる姿はまるでゾンビ(!)みたいでコワかった。それまでかなり精細に(あえていうなら執拗に)仕草をつけていただけに余計コワかった。
○マシュー・ベイカー『アメリカへようこそ』(田内志文訳、KADOKAWA)・・・・・・いい小説家見つけた。
○ロジェ・カイヨワ『石が書く』(菅谷暁訳、創元社)
○ルッツ・ザイラー『クルーゾー』(金志成訳、白水社)・・・・・・夏に読めて良かった。ジョン・ファウルズ『魔術師』のような世界。あれも名作だと思いますが、こちらは現実世界の崩壊との重ね合わせが味をより複雑にしている。
○長尾宗典『帝国図書館 近代日本の「知」の物語』(中公新書)
○ルネ・セディヨ『フランス革命の代償』(山﨑耕一訳、草思社)
○長谷部恭男『歴史と理性と憲法と 憲法学の散歩道2』(勁草書房)・・・・・・学海余滴の贅を尽くすエッセイ集シリーズ。良識を諄々と確認する姿勢が矯激に映るのは、もちろん世間が狂ってるからである。
○バート・S・ホール『火器の誕生とヨーロッパの戦争』(市場泰男訳、平凡社)
○元木幸一『ファン・エイク 西洋絵画の巨匠』(小学館)・・・・・・大きな本なので、エイクの精緻華麗なマティエールをなめるように観賞出来る。ヴェラスケスやルーベンスより、エイクやペトルス・クリストゥスの方が落ち着いて見られる。少なくとも夏はこちらのほうが暑苦しくはない。
○デイヴィッド・ホックニー他『はじめての絵画の歴史 「見る」「描く」「撮る」のひみつ』(井上舞訳、青幻舎インターナショナル)
○ジェームズ・チェシャー『地図は語る データがあぶり出す真実』(日経ナショナル・ジオグラフィック社)
○近衛典子他編『江戸の実用書』(ぺりかん社)
○山辺晴彦・鷲巣力『丸山眞男と加藤周一』(筑摩選書)
○榎本秋『戦国坊主列伝』(幻冬舎新書)
○エリザベス・タウンセンド『「食」の図書館 タラの歴史』(内田智穂子訳、原書房)・・・・・・このシリーズ、ちょっと質がよくない。どれもかいなでの記述で構成に工夫がない。せっかくの企画なのに、編集者は何をしておるのだ。
○田谷昌弘・萬福寺『萬福寺の普茶料理』(GAKKEN)
○北國新聞社出版局『鏡花文学賞50年』(北國新聞社)・・・・・なんと嵐山光三郎さんが受賞作全て(!)に解説をつけている。