以前ビネの作風を冗談まじりに「伝奇小説」と形容したことがある(当ブログ「鳥獣の王」2020.12.14)。新作を読んで、もう少しこれに注が必要と思った。 前言撤回というのではない。どころか、今回も話の結構は奔放を極め、というか荒唐無稽の域に達している。なにせ、あのインカ、ピサロなるごろつきによってあえなく征服されたまぼろしの帝国の皇帝アタワルパが、いいですか、こともあろうに(と言いたくなる)スペイン、当時の区分でいうところの神聖ローマ帝国をのっとってしまう(!)という筋書なのだから。そう、これはつまり十六世紀版ローラン・ビネ版の『高い城の男』なのである。
だから荒唐無稽。我が江戸の読本・合巻(の出来の悪いヤツ)や今なら異世界転生モノ(の出来の悪いヤツ)とは、しかし一線を画しているのは、げんなりするような出鱈目さや俗っぽいご都合主義のあの臭みがないからだ。
いやここらが微妙なところで、ちゃらんぽらんの具合やあきれるくらいの話の運び方が、にも関わらずある《軽み》のトーンで細心に整えられているから、読後莫迦莫迦しさを感じさせないというべきか。つまりは作者の意識がそれだけ精緻で尖鋭ということである。ローラン・ビネなのです。そうこなくてはならない。
分量からもまず明らかだろう。ノルマン人の一部族が新大陸をさすらい、あげく定住にいたる足取りを描いた神話的な、というかほぼ神話のパロディとなっている第一部(史実に照らせば十世紀ごろ)から、セルバンテスとエル・グレコが新大陸(ここではアメリカ大陸のことです)に渡る第四部のあいだに、アタワルパの「新大陸」(むろんインカ帝国の皇帝から見ての)上陸、神聖ローマ帝国皇帝カール五世との駆け引きと対決、宗教改革、神聖ローマの帝位獲得、社会体制の変革と侵略・反乱を叙述して四百頁に収めるというのは、強靱な意志なしにできることではない。
植民地政策や進歩史観、その根底にある西欧中心主義が厳しく断罪される現在だからこそ、地と図をひっくり返すというだけの思いつきは愚鈍(で軽薄な)な告発にとどまる。となればいっそ、歴史そのものを黒い笑いのなかに差し出すほか手はない、とユダヤ人虐殺や言語の夢魔的側面をかつて取り上げたビネは判断したのであろう。アタワルパの兄の執拗さ、メキシコ・イングランド連合(!)の残忍さ、スペイン異端審問所およびルターの頑迷不霊を見よ。
まあ、いかにもフランスの小説家らしく、ユーモアの側面にはいささか食い足りないところはあるけれども。ただ、カール五世の登場場面では少しばかり薄味ながら、この捉えどころのない「大」君主の肖像を辛辣に描き出している。
でもその分、やはりフランスらしく、あの懐かしいヴォルテールやディドロたちの哲学的コントの瀟洒で潑剌たる味わいは確実に見て取れる。アタワルパを南から来たカンディード(それともパングロス?)と見立てることはできないだろうか。
最後に思いつきひとつ。第三部のプレストの終わり方や、世界の不合理にあくまで晴朗に立ち向かう主人公の姿勢に、遠く十八世紀にまで遡らずとも、ウンベルト・エーコの『バウドリーノ』にビネはなにか得るところなかったかしらん(エーコのあの快作もまた哲学的コントの骨格をもった、「歴史改変」小説である)。


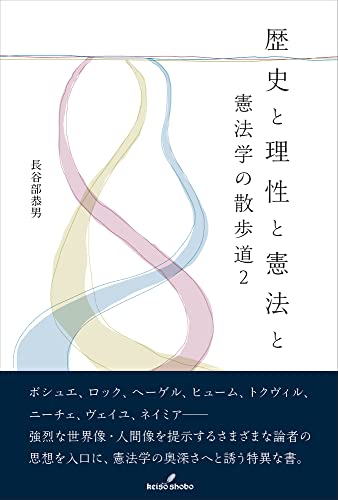

 *1
*1 *4
*4



